
PL法(製造物責任法)とは、「製造物」の「欠陥」が原因で、他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に賠償義務を負わせる法律のことです。
このページでは、まずPL法(製造物責任法)の意味や内容をわかりやすく解説します。
また、製造物についての予想されるリスクやその回避法、トラブル発生時の対処法についても解説しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
PL法(製造物責任法)とは?簡単に解説
PL法(製造物責任法)、「製造物」の「欠陥」が原因で、他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に損害賠償責任を負わせる法律です。
なお、PL法のPLとは、英語の”Ploduct Liability”の略であり、日本語の「製造物責任」を意味します。
他人の行為により、損害を受けた場合、損害賠償請求を行いますが、そのとき、被害者は加害者の「故意又は過失」について、立証しなければならないのが法律上の大原則です(民法709条)。
近年、様々な製品を入手できるようになり、生活の利便性が向上する一方で、欠陥製品の事故による被害者の数も急増していきました。
このとき被害者が製造業者の「故意や過失」の具体的な内容を立証することは簡単ではなく、酷であるという考え方が強く支持されるようになりました。
このような社会状況の変化を背景に、製造業者の「故意や過失」の有無を問わず、製品に「欠陥」があれば、製造業者の損害義務を認めるべきとして、1995年7月1日PL法が施行されました。
製造物責任を負うのはどのような場合か?

責任を負う主体
製造物責任法の責任を負うのは以下の①~③のいずれかに該当する者です(同法2条3項)。
①当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(製造業者)
販売業者や流通業者(運送業者・梱包業者・倉庫業者)は②、③に該当しない限り、製造業者には該当しません。
②自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者(氏名等の表示業者)
例)製品にブランド名を表示した事業者
③当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者(実質的な製造業者)
例)OEM製品やPB製品において「販売者」として表示されているが、実際には製造にも関与していた事業者
製造物責任法においては、①~③の3つをまとめて「製造業者等」といいます。
「製造物」とは?
製造物責任法において、「製造物」とは、製造又は加工された動産をいいます(同法2条1項)。
機械などの工業製品だけでなく、食品も含まれます。
動産が対象ですので、コンピューターのプログラムやサービス(修理や配送など)は「製造物」に含まれません。
「欠陥」とは?
製造物の「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(同法2条2項)。
一般的に、「欠陥」には、以下の3つの類型があるとされています。
◎ 製造上の欠陥
製造・管理工程に問題があることで、設計仕様どおりに製造されず、製品に安全性の問題がある場合
◎ 設計上の欠陥
設計自体に問題があることで、製品に安全性の問題がある場合
◎ 警告上の欠陥
製品パッケージ、説明書、製品本体にある使用上の指示や警告が不十分な場合
製造物責任が問題となる事案では、この「通常有すべき安全性」を備えていたか否かが争点となることが多い傾向です。
したがって、この点に関する裁判例を押さえておくことが重要なポイントとなります。
裁判例については、こちらのページで詳しく解説していますので、ぜひ御覧ください。
PL法(製造物責任法)の内容

損害賠償責任
製造業者等が、欠陥のある製造物を引き渡したことにより、他人の生命、身体、財産を侵害した場合、製造業者等は、これによって生じた損害を賠償しなければなりません(同法3条)。
免責事由
製造業者等が、以下の事項のいずれかを証明したときは、損害賠償責任を免れることができます。
① 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと(開発危険の抗弁)
② 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと
PL法(製造物責任法)の時効は2種類ある
PL法(製造物責任法)の3年の時効
製造物の欠陥による被害者又は法定代理人は、損害及び賠償義務者を知った時から3年間の間に製造業者等に損害賠償請求を行わなければならず、3年間を経過すると損害賠償責任は時効により消滅します(同法5条1項1号)。
PL法(製造物責任法)の10年の時効
また、製造物の引渡しから10年を経過した場合も、損害賠償責任を追及できなくなります(同法5条1項2号)。
上記の3年の時効との違いは、この場合、損害や賠償義務者を知らなくても、製品を受け取ってから10年以上経過すると損害賠償請求ができなくなるという点です。
ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じたときから上記の時効期間をカウントします(同法5条2項)。
PL法(製造物責任法)に対するリスクマネジメント
製造物責任を避けて通ることは不可能
製造物責任は、一般的に無過失責任と言われています。無過失責任とは、製造物の欠陥について、企業側に過失がなくても責任を負わせることを意味します。
製品を製造する企業である限り、どんなに注意していても欠陥製品を流通させてしまう可能性があります。
したがって、企業側としては、一定の欠陥製品が発生することを前提に、社内の危機管理体制を整備し、実際に消費者との紛争が生じた場合には、迅速に対応しなければなりません。
社内の危機管理体制の整備
製造物責任による会社の損害を最小化するためには、事前に社内の危機管理体制を整備しておくことが大切です。
以下のような点を考慮して、危機管理体制を整備することを検討すると良いでしょう。
 担当者・担当部署の選定
担当者・担当部署の選定 欠陥製品情報の蓄積
欠陥製品情報の蓄積 対応マニュアルの作成
対応マニュアルの作成 PL保険への加入
PL保険への加入
PL法への備えとしての保険
上で解説したように、欠陥製品を作ったメーカーの責任は重く問われています。
事故が発生した場合の賠償額はケース・バイ・ケースとなりますが、億単位の賠償額となることも決して珍しくはありません。
最悪のことを考えておくと、事故発生時の賠償義務をカバーできる保険に入ることをお勧めいたします。
PL法と表示義務について
PL法には、「危険」などの具体的な文言の表示を義務づける規定はありません。
しかし、危険が潜んでいる状況において、何も表示をしていないとそのこと自体が「欠陥」と認定されるおそれがあります。
したがって、注意の表示について必要性を検討することをお勧めいたします。
なお、PL法の責任にくわしい弁護士であれば、具体的にどのような表示をすべきかについて的確に判断できると思われますので、専門の弁護士に助言を求めると良いでしょう。
実際に欠陥製品をめぐる紛争が発生した場合の対応
欠陥製品が流通し、消費者の生命、身体、財産に損害が発生したことが発覚した場合は、迅速な対応が求められます。
欠陥製品は複数流通している場合があり、対応の遅れにより次々と紛争が発生し、企業の存続を脅かすほどの損害となるおそれもあるためです。
以下のような点に注意しましょう。
 事実関係の迅速かつ正確な把握
事実関係の迅速かつ正確な把握 所轄官庁への報告
所轄官庁への報告したがって、報告が必要となる所轄官庁を把握し、速やかに報告を行う必要があります。
 被害者への対応
被害者への対応
当事務所の弁護士に相談するメリット

事務所の企業法務部は、業種ごとに特化した弁護士が所属しており、製造業種に特化した弁護士がサポートを行います。
紛争が発生した場合の迅速な対応はもちろんのこと、紛争が顕在化する前であっても、専門的な立場から危機管理体制の整備方法など必要なアドバイスを行います。
担当者や担当部署に対する研修なども対応しております。
料金プラン
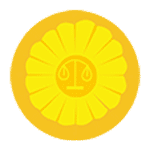 企業の相談料 初回0円
企業の相談料 初回0円
当事務所の顧問契約の内容・料金についてはこちらをご覧ください。
製造物責任法について、詳しくは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

