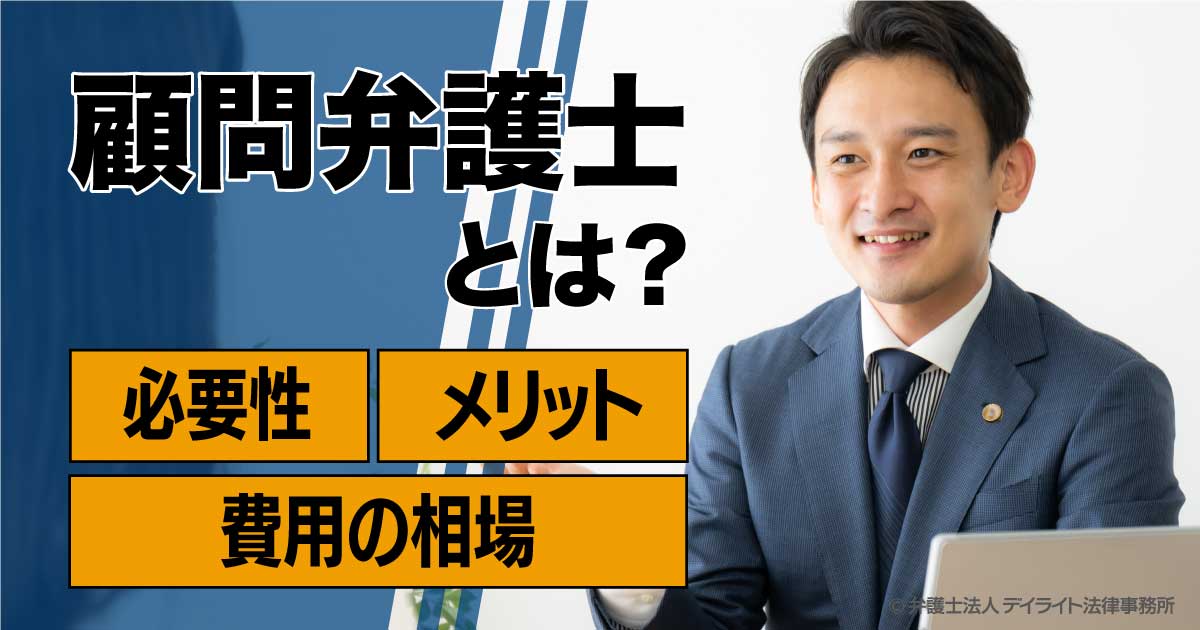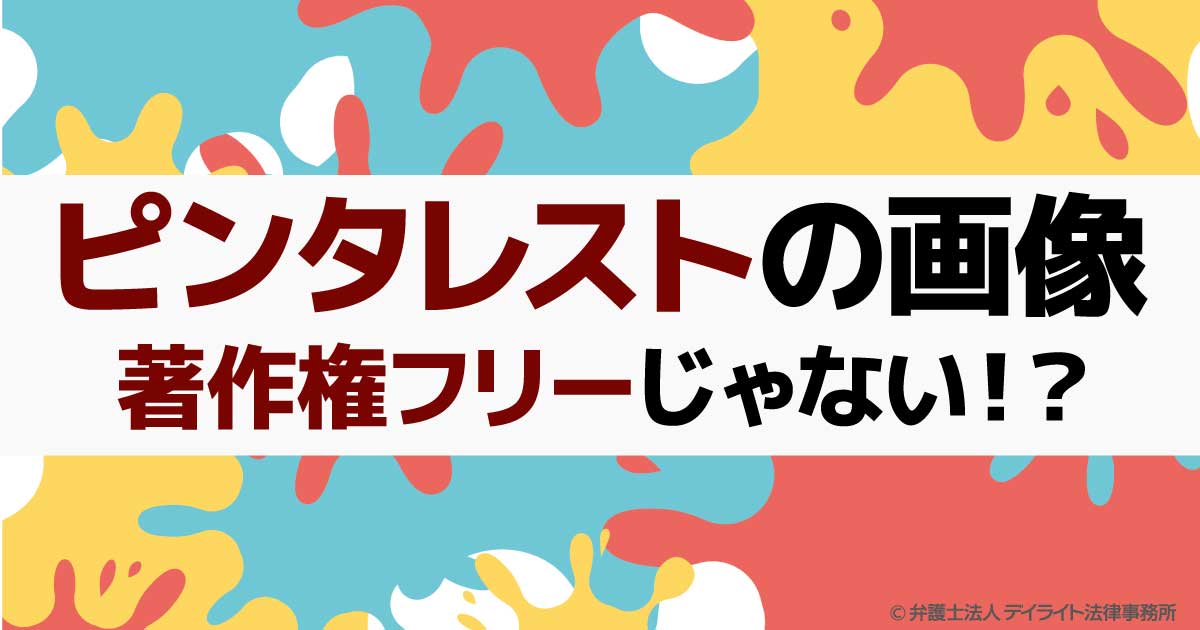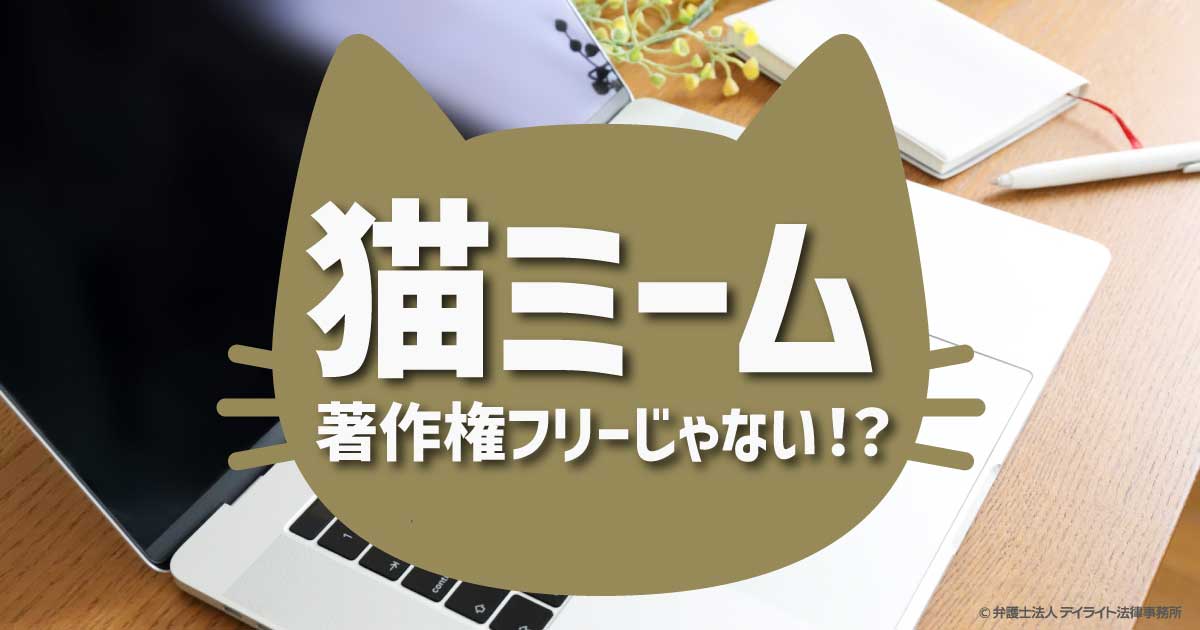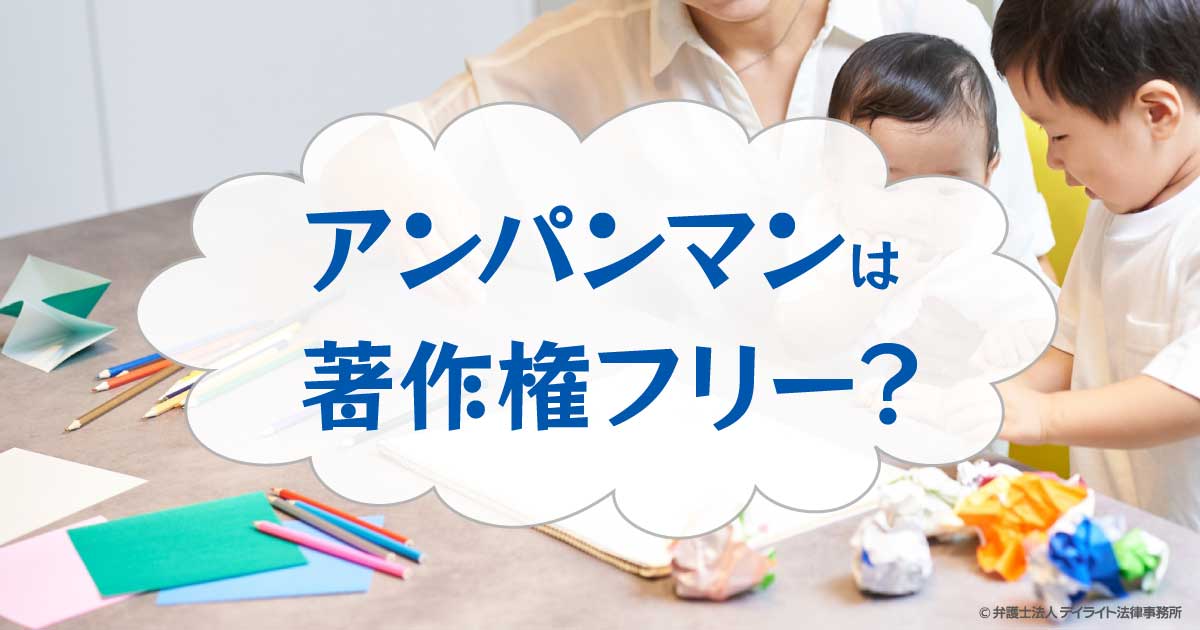弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
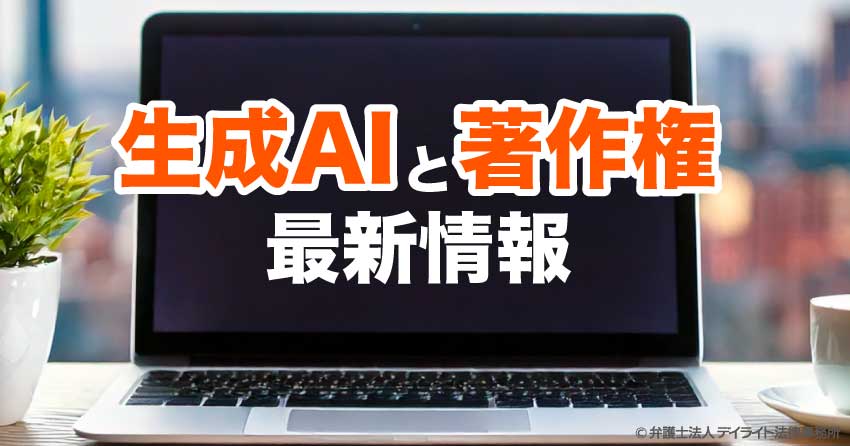
生成AIにより、文章や画像、音楽など、まるで人間が作ったかのようなクオリティの高いコンテンツをあっという間に生み出すことができるようになりました。
しかし、この便利な生成AIの利用にあたっては、著作権という法律の問題が避けて通れません。
この記事では、生成AIを利用するうえで誰もが知っておくべき著作権のルールについて、分かりやすく解説します。
生成AIを安心して、そして適切に活用するために、ぜひ最後までお読みください。
目次
生成AIとは?
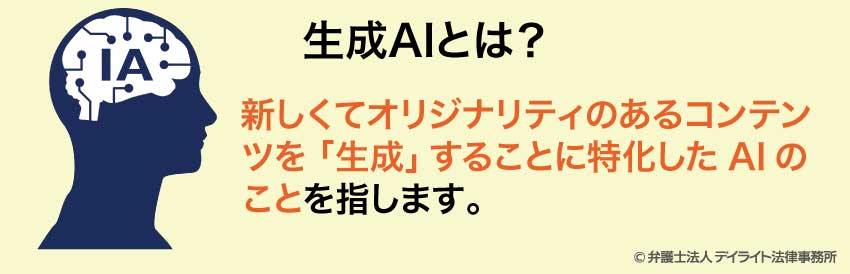
「生成AI(ジェネレーティブAI)」という言葉を最近よく耳にするようになったかと思います。
これは、新しくてオリジナリティのあるコンテンツを「生成」することに特化したAIのことを指します。
有名なChatGPTも生成AIの一つです。
文章、画像、音声、音楽、プログラムコードなど、様々な種類のデータから学習し、その学習結果をもとに、今まで存在しなかった新しいコンテンツを作り出すことができます。
例えば、ChatGPTのような対話型のAIに質問を投げかけると、自然な文章で回答が返ってきますが、これも生成AIの一つです。
また、指示をするだけで、高品質なイラストや写真を生成してくれる画像生成AIも登場しています。
このように、生成AIは私たちの創造活動や業務のあり方を大きく変える可能性を秘めています。
しかし、その仕組みや活用方法を正しく理解しておくことが、後の著作権に関する議論を理解する上で非常に重要になります。
生成AIの種類と仕組み
生成AIには、生成するコンテンツの種類によって様々なタイプがあります。
代表的なものとしては、文章を生成するAI(例:GPTシリーズ)、画像を生成するAI、音楽を生成するAI、そしてプログラムコードを生成するAI(例:GitHub Copilot)などがあります。
これらのうち複数の機能を持つAIも多いです。
これらの生成AIがどのようにして新しいコンテンツを作り出すのでしょうか?
その仕組みについても簡単に触れておきます。
まず、AIにはあらかじめ、大量の既存のデータ(テキスト、画像、音声など)を読み込ませて、その中から一定のパターンを学習させています。
ユーザーが「プロンプト」と呼ばれる指示を与えると、AIは学習したパターンをもとに、適切と思われる単語や画像、音などを組み合わせて、新しいコンテンツを生成します。
この「学習」や「生成」のプロセスにおいて、既存の著作物との関係で著作権の問題が発生する可能性があります。この点は、後ほど詳しく見ていきます。
生成AIの活用事例
生成AIは、すでに私たちの身の回りの様々な場所で活用されています。具体的な事例を見てみましょう。
文章の生成
会議の議事録作成やメールの作成、ブログ記事の下書きなど、ビジネス文書の作成でよく活用されています。
さらに、小説や脚本といったクリエイティブな文章作成の分野でも、アイデア出しや初稿作成のツールとして利用が広がっています。
画像やイラストの生成
例えば、広告デザイン、ウェブサイトの素材、プレゼンテーション用のイラストなど、多様なコンテンツがAIの活用によって生み出されています。
音楽の生成
動画のBGM、ゲーム音楽、オリジナルの楽曲制作などにもAIが活用されています。
特定のジャンルや雰囲気、使用したい楽器などを指定することで、AIが条件に合った楽曲を生成することができるようになっています。
コードの生成
ソフトウェア開発の現場では、特定の機能を実現するためのプログラムコードの一部をAIに生成させることができます。
また、欠陥を見つけるデバッグ作業の効率化にもAIが役立っており、開発期間の短縮につながっています。
生成AIと著作権の関係
生成AIと切り離せない関係にあるのが著作権です。
著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの分野で、人間の思想や感情を創作的に表現したものを保護するための権利です。
作品を作った人(著作者)に与えられ、その作品を無断でコピーしたり、インターネットで公開したり、上演したりすることを防ぐことができます。
AIが自らコンテンツを生成するようになったため、著作権ついて新しい議論が生まれています。特に重要なトピックについてご紹介します。
AIで生成した作品に著作権はある?誰に帰属する?
生成AIを使って文章や画像などを作り出したとき、その生成された作品に著作権は発生するのでしょうか?
日本の著作権法では、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。
そして、「著作者」とは「著作物を創作する者」とされています(著作権法第2条第1項第2号)。
つまり、著作権が認められるには「人間」によってその「思想又は感情」が「創作的に表現」されている必要があるわけです。
したがって、現在の日本の著作権法では、AIそのものが単独で生成した作品には、著作権は認められないと考えられています。
では、人間が生成AIを使って作品を作った場合はどうなるのでしょうか?
もし、人間が生成AIを単なる道具として利用し、人間の思想や感情が創作的に表現されたといえる場合には、その作品は人間の著作物となり、著作権はその人間に帰属すると考えられます。
この場合、人間がどのような指示(プロンプト)を与えたのか、生成された結果をどのように選んで、編集・加工したのか、といった人間の創作的な貢献があるかどうかが重要になります。
例えば、イラストレーターが画像生成AIを使ってキャラクターのラフ案を複数生成させ、その中からイメージに合うものを選んで、加筆や修正を加えて最終的なイラストを完成させた場合であれば、最終的なイラストはイラストレーターの著作物となり得ます。
一方、単にAIに漠然とした指示を与えただけで、生成されたものをそのまま利用した場合には、人間の創作的な貢献がほとんど認められないことになります。
この場合には、著作権が発生しない可能性が高いです。
この境界線は曖昧ですので、今後の裁判例などの積み重ねによって判断基準が作られていくことになるでしょう。
文化庁では、AIと著作権の考え方についてその見解を公表しています。
各種資料も公表されていますので、ご参考にされてください。
AIで生成した作品を利用する場合の注意点
AIで生成した作品を、私たちが利用する際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
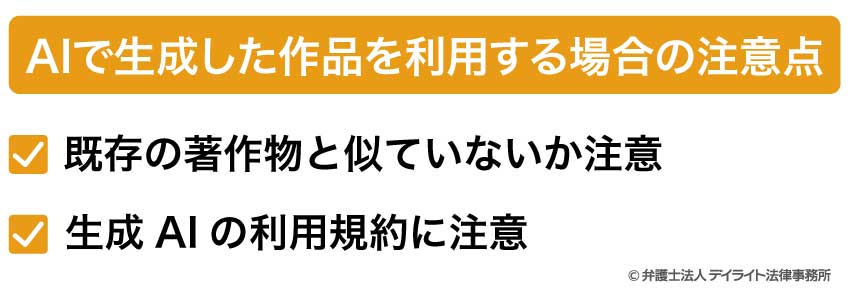
既存の著作物と似ていないか注意
最も重要なのは、生成された作品が、意図せず既存の著作物と似てしまったり、あるいは直接的に既存の著作物を複製してしまったりするリスクがあるということです。
AIは大量のデータを学習してコンテンツを生成します。
その学習データの中には、著作権によって保護されている画像や文章、音楽などが含まれています。
AIが生成する過程で、学習データに含まれる特定の著作物の特徴を強く反映してしまい、結果として生成された作品が既存の著作物と酷似してしまう可能性がゼロではありません。
もし、生成した作品が既存の著作物と類似しており、かつ依拠性(既存の著作物を知っていて、それを元に創作したこと)が認められると判断された場合、著作権侵害となる可能性があります。
したがって、生成AIで作成したコンテンツを公開したり、商用利用する場合には、事前に、既存の著作物との類似性がないか、十分に確認することが非常に重要です。
特に、有名なキャラクターやデザイン、歌詞、メロディーなどに似ていないか、慎重にチェックする必要があります。
生成AIの利用規約に注意
次に注意すべき点は、利用している生成AIの利用規約を確認することです。
多くの生成AIサービスは、利用規約の中で、生成されたコンテンツの著作権の帰属や、利用方法に関するルールを定めています。
例えば、「生成されたコンテンツの著作権はユーザーに帰属する」としているサービスもあれば、「サービス提供者とユーザーが共同で著作権を持つ」、「著作権はサービス提供者に帰属する」としているサービス、あるいは「商用利用には制限がある」といった条件を設けているサービスもあります。
利用規約の内容をよく理解せずに利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特に、生成したコンテンツをビジネスで利用したり、販売したりする予定がある場合は、利用規約をしっかりと確認し、許諾された範囲内で利用することが不可欠です。
以上の通り、生成AIで作成した作品を安全に利用するためには、事前の確認と利用規約の遵守が非常に重要になります。
もし、生成されたコンテンツの著作権について少しでも不安がある場合は、知的財産権に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
生成AIによる著作権侵害のリスク
生成AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。
詳しく見ていきましょう。
著作権侵害とは?
著作権侵害とは、著作権法によって著作者に認められている権利(著作権)を、正当な理由なく侵害する行為を指します。
具体的には、著作者の許諾を得ずに著作物を複製したり、インターネットで公衆送信したり、翻案(元の著作物を改変して新しい著作物を作ること)したりすることが著作権侵害にあたります。
著作権侵害は、著作権者から差止め請求(侵害行為をやめるように求めること)や損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、悪質な場合には刑罰の対象にもなり得ます。
AIが学習データとして著作物を利用する行為について
生成AIは、大量のデータから学習することで性能を向上させます。
この学習データには、ウェブサイト上の文章や画像、音楽など、様々な著作物が含まれている可能性があります。
これらの著作物を著作権者の許諾なくAIの学習に利用することが、著作権侵害にあたるのではないか、という議論があります。
これについて、日本では著作権法第30条の4という条文がポイントになります。
情報解析(AIによる学習を含む)の目的であれば、著作権者の利益を不当に害さない限り、著作物を利用できるとされています。
ただし、この条文の解釈についてはまだ議論の余地があります。
特に、どのような場合に「著作権者の利益を不当に害する」にあたるのかは、個別のケースによって判断が分かれる可能性が高いです。
AIが既存の作品を模倣してしまう可能性
前のセクションでも触れましたが、AIが学習したデータに含まれる著作物の特徴を強く反映してしまい、生成された作品が既存の著作物と酷似してしまうリスクがあります。
具体的には、生成AIは、学習データに含まれるパターンやスタイルを学習しますが、この学習プロセスにおいて、AIが特定の既存作品の特徴を強く「模倣」してしまう可能性が指摘されています。
このような模倣のリスクを完全に排除することは現状では難しいですが、生成されたコンテンツが既存の作品と不当に類似していないか、人間の目で確認する作業は不可欠です。
特に、有名な作品や、著作権保護期間がまだ切れていない作品に類似していないか、慎重な確認が必要です。
生成した作品が既存の作品と類似してしまう可能性
AIが生成した作品が、意図せず既存の作品と似てしまう可能性もあります。
単なる偶然の一致のように見えても、著作権侵害とされてしまうリスクがあります。
ここでも、著作権侵害の要件である依拠性(元の作品を知っていたこと)と類似性が問題となります。
AIの場合、学習データとして既存の著作物を利用しているため、生成された作品が学習データに含まれる特定の著作物と類似している場合、依拠性が認められやすいと考えられます。
つまり、AIがその著作物を「知っていた」とみなされる可能性があるのです。
生成AIを利用してコンテンツを作成し、それを公開したり利用したりする際には、生成されたものが偶然にも既存の作品と似ていないか、そして著作権侵害のリスクがないか、慎重に確認するプロセスが非常に重要になります。
ご自身で依拠性などの法的な判断をするのは難しい場合もあると思いますので、その場合は知的財産を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
AIによる著作権侵害の事例
生成AIが登場してからまだ日が浅いため、生成AIによる著作権侵害を直接的に認めた日本の裁判例は、現時点ではまだ多くありません。
しかし、海外ではすでにいくつかの事例が報道されており、今後の日本での議論や判例の形成に影響を与える可能性があります。
アメリカでは、作家などの著作者が、生成AIシステムの学習に著作物が無断で利用されたとして、生成AIを提供しているテクノロジー企業複数を相手にして訴訟を起こしています。AIが大量の著作物を収集・利用して学習することの適法性が問われており、今後の法的な整理に大きな影響を与える可能性があります。
参考:OpenAI denies infringement allegations in author copyright cases|ロイター通信
中国では、生成AIによる「ウルトラマン」によく似た画像について、生成AIサービス事業者に著作権侵害の責任が認定される判決が出ています。
参考:「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令|読売新聞オンライン
アメリカでは、有名なハリウッド女優が自身の声を勝手にAIの音声に使われていると主張して法的措置を検討していることが話題になっています。
参考:OpenAIの最新モデル「GPT-4o」にスカーレット・ヨハンソンが激怒、くすぶる倫理課題|朝日新聞Globe+
アメリカにて、有名な音楽レーベルが集団で音楽生成AIを提供する事業者を相手に訴訟を起こした事例があります。
参考:音楽生成AIに大手レーベルが“宣戦布告”、法廷に持ち込まれた「著作権侵害」の行方|WIRED
その他、音楽生成AIを使って楽曲を制作し、それを公開・販売したところ、既存の有名な楽曲とメロディーやコード進行が酷似しているとして、著作権者からクレームを受けた、あるいは訴訟に発展したという事例もあります。
特に、AIが生成した楽曲が既存の楽曲と類似しているかどうかの判断は専門的な知識を要する場合が多く、音楽の専門家や弁護士の意見が必要となることがあります。
現時点では、以上のような事例でも明確な法的判断が出ていない状況です。日本においける今後の法改正や裁判例の動向を注視していくことが必要になります。
生成AIによる著作権侵害を避けるための対策
続いて、生成AIによる著作権侵害を避けるための具体的な対策について解説します。
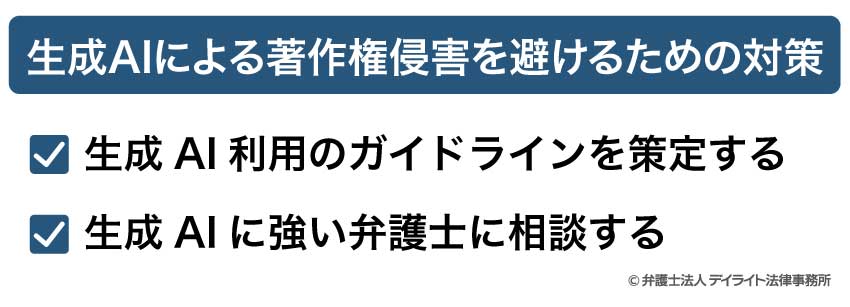
生成AI利用のガイドラインを策定す
企業や組織で生成AIを導入・利用する場合、従業員がどのような点に注意して生成AIを利用すべきかを明確にするための「生成AI利用ガイドライン」を策定することが非常に有効です。
ガイドラインには、生成AIの利用目的や範囲、利用しても良いデータの種類、そして特に著作権に関する注意点などを具体的に記載します。
ただし、ガイドラインは一度作ったら終わりではありません。生成AIの技術や法的な議論は日々進化しています。
そのため、定期的にガイドラインを見直し、最新の状況に合わせて内容をアップデートしていくことが重要です。
生成AIに強い弁護士に相談する
生成AIと著作権に関する問題は、比較的新しい分野であり、その法的な解釈や実務はまだ確立されていない部分が多くあります。
そのため、生成AIを利用する上で著作権に関する懸念が生じた場合や、実際に著作権侵害の可能性が疑われる事態が発生した場合には、生成AIに関する問題に詳しい弁護士に相談することが最も有効な対策です。
当事務所でも、企業のIT・知財戦略に詳しい弁護士が、生成AIに関する法務問題のご相談を承っております。
お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
会社法務に強い弁護士へ相談するメリットや、顧問弁護士については、以下のページをご覧ください。
生成AIに関する著作権法の現状と課題
著作権法における生成AIの扱い
現在の日本の著作権法において、生成AIに関する規定が直接的に設けられているわけではありません。
しかし、既存の条文を生成AIに関連する事柄にどう適用するのか、という議論が行われています。
AIが著作物を学習データとして利用する行為については、著作権法第30条の4が関連します。
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
〜〜〜
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)のように供する場合
〜〜〜
この条文は、著作権者の権利を不当に害しない限り、情報解析(AIによる学習を含む)のために著作物を利用できると規定しています。
ただし、生成AIの学習利用にどこまで適用できるのか、どのような場合に著作権者の利益を不当に害するのか、といった点については解釈が分かれる可能性が残っています。
また、AIが生成したコンテンツに著作権が認められるかどうかについては、日本の著作権法では「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」が著作物と定義されているため、AI単独の創作には著作権は認められない、というのが一般的な見解です。
人間が生成AIをツールとして利用し、人間の創作的な貢献が認められる場合に、人間の著作物として著作権が発生すると考えられています。
しかし、どの程度の関与があれば人間の著作物と認められるのか、その線引きは明確ではありません。
このように、現在の著作権法では、生成AIに関する様々な問題に対して、既存の条文を解釈で対応しようとしていますが、限界があることも指摘されています。
生成AIに関する法的整備の動向
生成AIの急速な発展を受けて、日本でも生成AIに関する法的な課題について活発な議論が行われています。
文化庁の審議会(著作権分科会)でも、生成AIと著作権の問題が集中的に検討されており、複数の文書が取りまとめられ、公表されています。
今後も議論は続けられ、法改正による明確化が図られると思われます。
AIによる創作活動を促進し、技術革新を後押しする一方で、著作権者の権利を適切に保護し、クリエイターの創作意欲を損なわないような制度設計を期待しているところです。
最新の議論の状況については、文化庁のウェブサイトなどで公表される情報をご確認ください。
引用:AIと著作権に関する考え方について|文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会
生成AIに関する海外の法規制事例
海外のAIに関する動向についても簡単に見ておきましょう。
アメリカでは、2023年、バイデン大統領により「人工知能(AI)の安心、安全で信頼できる開発と利用に関する大統領令」が発令され、アメリカの連邦機関がAI導入に関して守るべきルールなどを定めています。
また、著作権局でも、AIが作った芸術作品に著作権はないことや、AIで作成した絵は著作権で保護されないことなどが宣言されるなど、政府のスタンスが明確に示されてきました。その他、州別での法整備も進んでいます。
欧州連合(EU)でも、2024年5月21日に「欧州(EU)AI規制法」が成立し、規制内容に応じて2030年12月31日までに段階的に施行されます。
欧州AI規制法では、AIシステムをリスクレベルに応じて分類し、リスクの高いAIに対しては、学習データの品質や透明性、人間の監視の必要性などの義務を課すことが盛り込まれています。
また、中国では、生成AIサービス提供者に対し、生成されたコンテンツの合法性や、サービス利用者の本人確認などに関する義務を課す規制が導入されています。
生成されたコンテンツが国家の安全や社会の公共の利益を害するものであってはならない、といった内容も含まれています。
これらの海外の動向は、日本の今後の法整備に影響を与える可能性があります。
日本も、国際的な調和を図りつつ、日本の実情に合った生成AIに関する法的なルールを整備していくことが求められているのが現状です。
生成AIと著作権に関するFAQ
続いて、生成AIと著作権に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
![]()
生成AIで作ったコンテンツを販売することはできますか?
一方で、人間が生成AIをツールとして利用した場合で、創作的な加工や編集を加えた場合は、人間の著作物として著作権が発生する可能性があります。
著作権が発生しているコンテンツであれば、原則として著作権者であれば自由に利用(販売を含む)することができます。
ただし、生成されたコンテンツが、意図せず既存の著作物に類似していないかは必ず確認しましょう。
もし、生成されたコンテンツが既存の著作物と類似しており、かつ依拠性が認められると判断された場合、たとえ人間の創作的な加工が加えられていても、元の著作物の著作権を侵害しているとして、販売が差し止められたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。
また、前述の通り、生成AIサービスの利用規約も必ず確認しましょう。
サービスによっては、生成されたコンテンツの商用利用に制限がある場合があり、販売も認められないことがあります。
![]()
AIによる画像生成は違法ですか?
しかし、この記事で見てきたように、著作権の侵害になるような画像の生成は違法となる恐れがあります。
また、他者の権利(肖像権、パブリシティ権など)を侵害する画像を生成・利用することも違法あるいは利用差止や損害賠償を受けるリスクがありますので注意が必要です。
特に、生成した画像をインターネットで公開したり、商品として販売したりする際には、これらのリスクが顕在化しやすくなります。不安な点があれば、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
ここまで、生成AIと著作権の関係について、基本的な知識から著作権侵害のリスク、そしてそれらを避けるための対策までを詳しく解説してきました。
今後、生成AIは仕事でもプライベートでも欠かせないツールになることが予想されます。
しかし、その便利さの裏側には、著作権という法律の問題が潜んでいます。
そして、生成AIと著作権に関する法的な議論はまだ道半ばです。
特に会社では、法務部門などで議論の動向を把握し続けることが重要です。
もし、この記事を読んで、生成AIと著作権についてもっと知りたいと思った方や、具体的なケースでどう判断すれば良いか不安に感じた方がいらっしゃいましたら、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
デイライト法律事務所では、生成AIやIT関連の法務問題に詳しい弁護士が、皆さんの疑問や不安にお答えし、適切なアドバイスを提供させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。