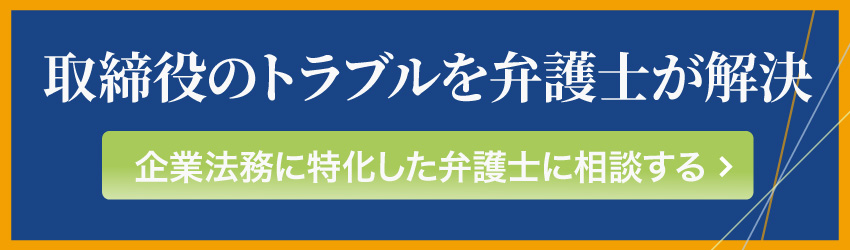弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
取締役の選任
 取締役の選任は、株主総会決議によって行います。
取締役の選任は、株主総会決議によって行います。
この決議は、普通決議とされています。すなわち、議決権を行使することのできる株主の過半数以上の株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数が賛同すれば選任されます。
取締役の欠格事由
会社法は取締役になれない者について以下のとおり定めています(会社法331条)。
・法人
・成年被後見人若しくは被保佐人
・会社法、一般法人法、金融商品取引法及び破産法等の倒産法制度の犯罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・上記以外の犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまで(執行猶予中を除く)
取締役は株式会社の意思決定を行う機関である以上、法人は取締役になれないこととされています。また、意思能力に制限がある成年被後見人や被保佐人も取締役にはなれません。
以前は、破産者も欠格事由とされていましたが、現在の会社法では欠格事由となっておらず、破産者でも取締役に就任することは可能です。
他方で、会社法関連での犯罪を犯した者は、刑の執行後2年間は取締役に就任することができないことになっています。
取締役の人数
 取締役会設置会社の場合は、取締役は3人以上である必要があります(会社法331条4項)。しかしながら、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役は1人でもよいとされています。
取締役会設置会社の場合は、取締役は3人以上である必要があります(会社法331条4項)。しかしながら、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役は1人でもよいとされています。
取締役の人数については、定款で最低限、最高限の人数を定めておくことができます。
取締役の任期
取締役の任期については、公開会社かどうかで違いがあります。
すなわち、公開会社の場合、取締役の任期は2年間です(会社法332条1項)。この期間は定款又は株主総会決議で短縮することができますが、2年間以上に伸長することはできません。
他方で、非公開会社の場合には、定款で10年間まで任期を伸ばすことができます。実際に非公開会社の多くで取締役の任期を10年間に設定しているのが現状です。
取締役の解任
取締役と会社の関係は雇用ではなく、委任関係です(会社法330条)。したがって、取締役は、任期中いつでも株主総会決議により解任されることがあり得ます。
この場合の株主総会決議も選任の場合と同じく普通決議で足ります(会社法341条)。ただし、定款で過半数以上の割合を要求するよう定めることは可能です。
解任された取締役は、正当な理由がある場合を除いて、解任によって生じた損害の賠償を会社に請求することができることになっています(会社法339条2項)。具体的には、任期満了までの役員報酬を請求することが考えられます。
取締役は、株式会社の業務執行権を掌握する非常に重要な機関です。したがって、どのような人を取締役に就任させるか、あるいは解任するかは会社の運営を左右することになります。
会社の構成についてお困りの方は、専門の弁護士にご相談ください。