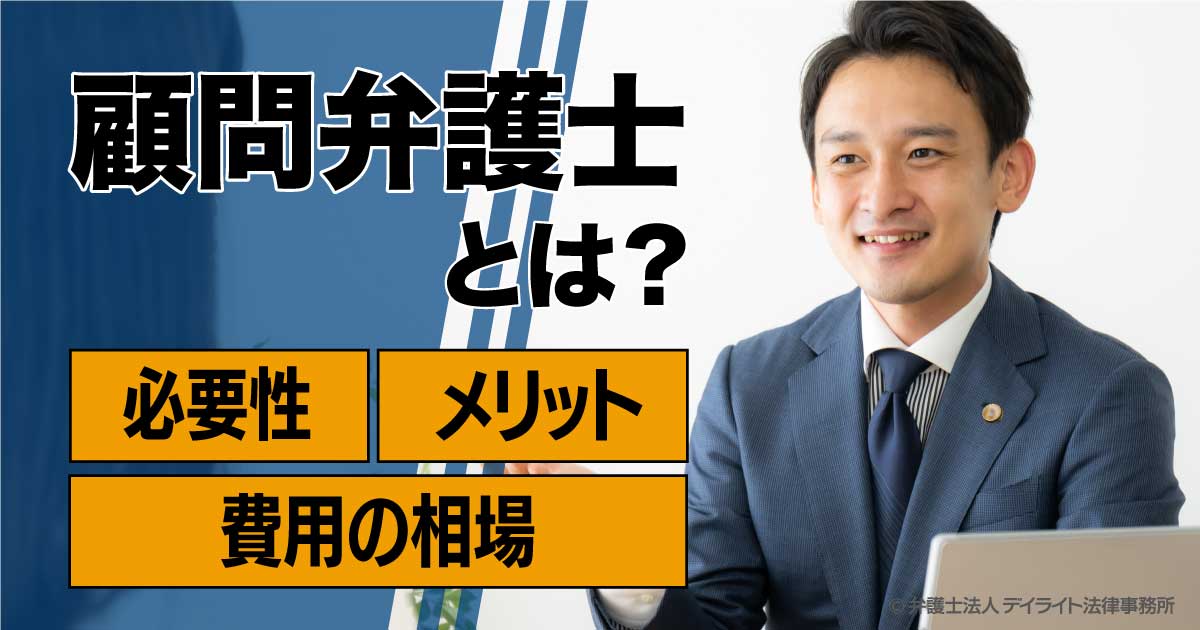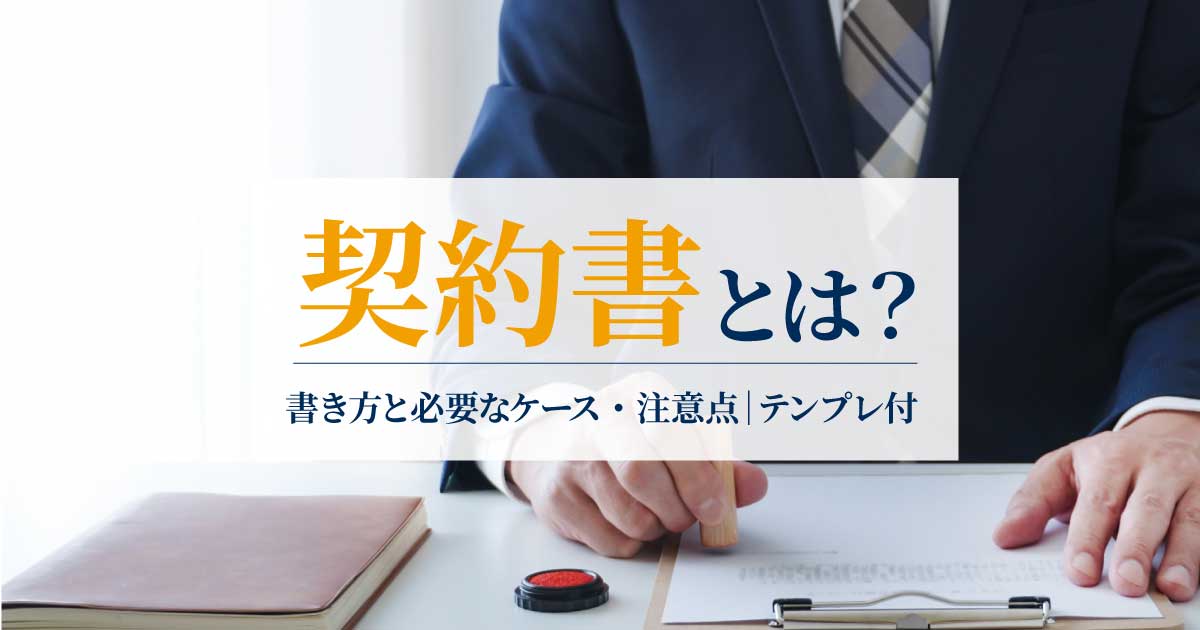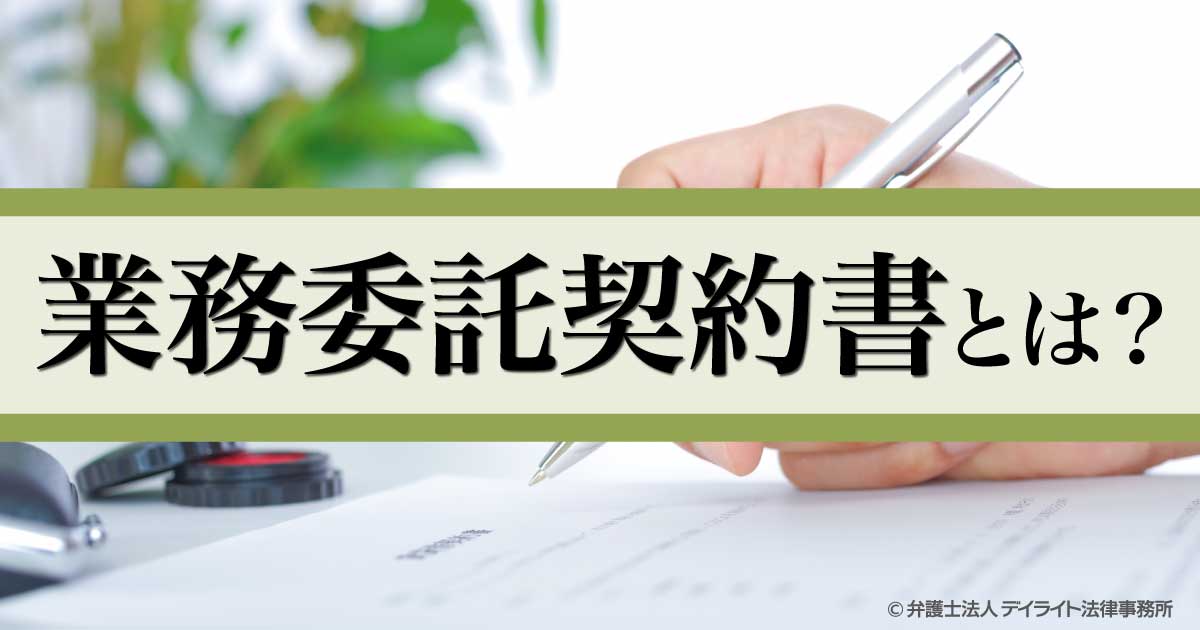弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
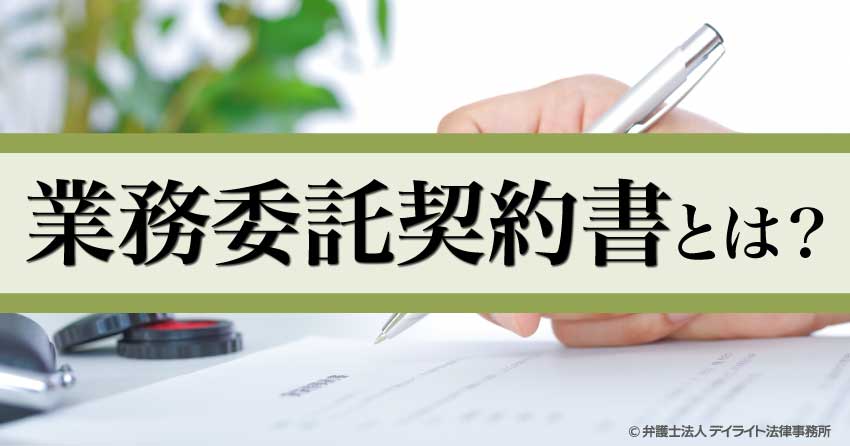
業務委託契約書は、業務委託(他人に一定の仕事を依頼すること)を行う際に用いられる契約書で、日常の取引において頻繁に登場する契約書です。
業務委託契約書は、委託する業務の内容に応じて、さまざまな形態があります。
この記事では、業務委託契約書の意義や活用場面を紹介したうえで、業務委託契約書のひな形および書き方を詳しく説明しています。
また、業務委託契約書の注意点についても説明していますので、この記事をお読みいただければ、業務委託契約書のひな形を確認しつつ、どのような点について気を付けるべきかを知ることができます。
業務委託契約書とは
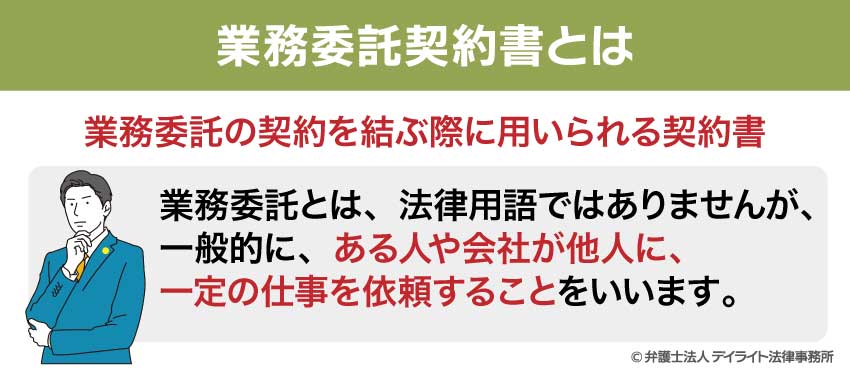
業務委託契約書は、業務委託の契約を結ぶ際に用いられる契約書です。
業務委託とは?
業務委託とは、法律用語ではありませんが、一般的に、ある人や会社が、他人に一定の仕事を依頼することをいいます。
売買契約や賃貸借契約など、日常的によく目にする契約の多くは、民法に定められている契約類型であるため、民法の規定が適用されます。
しかし、民法には「業務委託」という契約の類型は定められていません。
そのため、業務委託契約はその具体的な内容に応じて、民法のどの契約の性質を有するのかを判断する必要があります。
業務委託契約の性質
業務委託契約の性質は、大きく分けると2つあります。
1つは、法律行為や法律行為以外の事務処理を他人に依頼する「委任(準委任)契約」の性質を持つものです。
もう1つは、物品を制作することや、工事などの一定の仕事を完成することを他人に依頼する「請負契約」の性質を持つものです。
なお、業務委託契約の内容によっては、請負と委任(準委任)の両方の性質を持つ場合もあります。
請負契約も委任(準委任)契約も、民法に定められた契約類型です。
そのため、業務委託の内容に応じて、民法の請負または委任(準委任)の規定が適用されることとなります。
請負と委任の違いは、一定の成果物の完成が約束されているかどうかです。
請負の場合には、成果物の完成が約束されている契約となります。
例えば、家の建築です。家の建築では、設計図にしたがった家を建てることが契約内容となりますが、この家が「成果物」です。
これに対し、委任では、必ずしも成果物の完成が約束されていません。具体例としては、弁護士への依頼です。
弁護士は結果を約束するのではなく、法律事務の処理を依頼されるというものですので、請負と違って、成果物が必ずできるわけではありません。
業務委託契約では、他者に一定の仕事を依頼する側を「委託者」、依頼を引き受けて仕事をする側を「受託者」と呼びます。
業務委託契約書では、当事者のことを「委託者」、「受託者」という言葉で表されることも多いです。
この記事でも、「委託者」、「受託者」という言葉を使って説明します。
業務委託契約書が活用されるケース
会社の場合でも個人であっても、ビジネスを行うに際して、自分ですべての業務を行うのは非効率的であるという場面は多いでしょう。
そのような場合には、外部の第三者に業務の全部または一部を委託することによって、業務を効率化したりコストを削減することができます。
業務委託契約の典型例としては、ビルの管理業務やコンサルティング業務、アドバイザリー業務などが挙げられます。
これらは法律行為ではない事務の委託であるため、準委任に該当します。
このような業務を他人に委託する場合に、業務委託契約書が活用されます。
業務委託契約は、口頭での合意によっても有効に成立するため、必ず契約書を作成して締結しなければならないというわけではありません。
しかし、委託業務の内容や範囲、委託料の支払や契約の解除、損害賠償など、書面によって明確にしておくべき事項は多岐にわたるため、業務委託契約書を作成するのが一般的です。
業務委託契約と雇用契約との違い
誰かに仕事を任せるという点でいえば、「雇用」が思い浮かぶと思います。
業務委託と雇用契約ではどのような違いがあるのでしょうか?
業務委託と雇用契約の違いを表でまとめると以下のようになります。
| 業務委託契約 | 雇用契約 |
|---|---|
|
|
雇用契約とは、従業員が会社に対して労働をすることを約束し、会社がこれに対して対価(給料)を支払うことを約束することで成立する契約です。
雇用契約では、従業員は会社の指揮監督を受けて業務を行います。
例えば、会社は、従業員の業務遂行に関する細かい指示や指導、勤務場所や労働時間の管理などを行います。
これに対して、業務委託契約では、依頼内容についての要望や指示はあるものの、受託者は委託者の細かい指揮監督を受けることはありません。
あくまで独立した当事者同士の契約という関係です。
そのため、雇用契約のように日々の業務管理は行われず、勤務場所や労働時間も原則として自由です。
いわゆるフリーランスもこの業務委託契約に該当します。
雇用契約では、労働基準法や労働契約法、労働組合法などの労働関係法令が適用されます。
そのため、従業員は、残業代や休日労働の割増賃金の発生や休日、有給休暇など、労働関係法令による保護を受けることができます。
一方、業務委託契約では原則としてこれらの労働関係法令は適用されないため、残業代や休日、有給休暇などは発生しません。
このように業務委託と雇用契約では、その性質が大きく異なります。
フリーランスについては、いわゆるフリーランス法という法律が制定されています。
詳しくはこちらもご確認ください。
業務委託契約書のひな形
業務委託契約を締結する際には、ひな形(テンプレート)を利用することで、一から契約書を作成するよりも労力や時間を節約できます。
業務委託契約書のテンプレート
以下のリンク先では、一般的な業務委託契約書のテンプレートを掲載しています。
テンプレートは、どなたでも無料でダウンロードすることができます。
この記事の説明とあわせて、是非ご活用ください。
業務委託契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)を無料でダウンロードいただけます。
業務委託契約書の書き方
一般的な業務委託契約書に記載するべき内容として、以下のものが挙げられます。
- ① 委託する業務の内容
- ② 対価と支払い条件
- ③ 業務の遂行方法
- ④ 再委託の可否
- ⑤ 秘密保持
- ⑥ 解除
- ⑦ 反社条項
- ⑧ 損害賠償
- ⑨ 契約期間
- ⑩ 協議事項、準拠法及び紛争の解決
① 委託する業務の内容
委託者が受託者に委託する業務の内容を記載します。
受託者は、ここで記載された内容を受託業務として行いますので、どのような業務内容であるのかが明確になるよう、正確かつ具体的に記載する必要があります。
委託業務の内容によっては、契約書上に全てを具体的に記載することが難しいこともありますが、当事者間での後のトラブルを防ぐために、できる限り具体的な内容を記載し、あいまいにならないようにしましょう。
②対価と支払い条件
委託業務の対価(業務委託料)を記載します。
業務委託契約の内容が委任(準委任)に分類される場合には、民法上は、無報酬が原則であることから、対価が発生するのであれば必ず記載しておく必要があります。
対価の支払時期や支払方法についても具体的に記載しましょう。
請負の場合には、着工時に30%、中間地点で30%、完成時に40%のように出来高払いのことも多いですが、こうした条件もきちんと契約書に反映しておかなければなりません。
③業務の遂行方法
委託業務の遂行の具体的な方法について、特に明確にしておくべき事項を記載します。
例えば、委託業務について、完成品(成果物)がある場合には、その納品日や納品場所、納品方法などを定めます。
④再委託の可否
再委託とは、業務委託の受託者が、委託者から委託を受けている業務の全部または一部について、さらに他の第三者に委託することをいいます。
再委託は、受託業務のボリュームが多い場合や、第三者に委託したほうが効率的に委託業務を遂行できる場合などに有効な方法です。
その一方で、委託者としては、あくまでも受託者を信頼して業務委託契約を結んだのであって、他の第三者に再委託してもらいたくないというケースもあります。
そのため、業務委託契約書には、再委託の可否についての条項を必ず設けるべきです。
再委託を認める場合であっても、信頼の置けない第三者に再委託することを防ぐために、事前に委託者の承諾を得ることを条件とするのが一般的です。
再委託先の候補が適切かどうかを委託者が判断できるようにするために、受託者に対して、事前に再委託先候補に関する情報を委託者に通知しなければならない旨を明記することもあります。
具体的には、再委託先候補の名称、住所・本店所在地、再委託する業務の内容及び範囲などを通知するよう定めます。
⑤秘密保持
委託業務を遂行するにあたって、当事者間でやり取りをする情報を保護するための規定です。
外部に漏れたり相手方に不正利用されたりすると大きな被害を受ける可能性がある、重要な情報を開示する場合には、必ず規定しましょう。
なお、顧客の情報など、個人情報のやり取りが生じる場合には、相手方に慎重な取り扱いを求めるために、秘密保持条項とは別に、個人情報の取り扱いに関する条項を設けることもあります。
⑥解除
どのような場合に業務委託契約を解除することができるかを具体的に記載します。
⑦反社条項
反社とは、暴力団などの「反社会的勢力」の略語であり、反社条項は、反社会的勢力を排除する条項です。
反社条項によって、契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力である場合や、反社会的勢力と一定の関係を持っている場合などにおける対応を定めます。
具体的には、相手方が反社会的勢力であったり、反社会的勢力と関係を持っていることが判明した場合には、催告をすることなく、直ちに契約を解除できることを定めます。
さらに、契約を解除した場合には損害の賠償や補償などを一切行わないことを明記することもあります。
反社条項は、業務委託契約書に限られず、企業が結ぶ契約書において一般的に設けられる規定です。
企業は、その社会的責任や企業防衛などの観点から、反社会的勢力とは一切関わりを持たないことや、反社会的勢力による不当な要求には断固として応じないことが求められているからです。
⑧損害賠償
当事者が契約に違反して相手方に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負う旨を明記します。
⑨契約期間
業務委託契約の期間を定めます。
継続的に取引を行うことを予定している場合には、当事者から契約期間が満了する一定の期間内に申し出がなければ、自動的に更新される旨を定めます。
⑩協議事項、準拠法及び紛争の解決
当事者間で予期せぬ争いを未然に防ぐために、契約書に定められていない事項や、契約書の解釈に食い違いが生じたなどの場合には、当事者間で誠実に協議の上、解決することを明記することが多いです。
また、準拠法(今回の取引にどの国の法律が適用されるか)や合意管轄(法的紛争が裁判に発展した場合にどの裁判所に訴えを提起すべきか)についても、あらかじめ契約書に明確に定めておきます。
通常は、委託者の側が契約書案を作成して、受託者にその内容を確認してもらうという手順になります。
委託業務の内容や範囲、業務遂行における特記事項、対価などは、まずは業務を委託したいと考える委託者の側が設定し、受託者に提示するべきだからです。
受託者は、委託者が設定した契約内容に異議がなければ、委託者が作成した契約書案の内容で契約を締結します。
これに対し、受託者に異議がある場合には、条件面その他について受託者と交渉や協議を行ったうえで、お互いが同意した内容に修正して、契約を締結することになります。
業務委託契約書の注意点
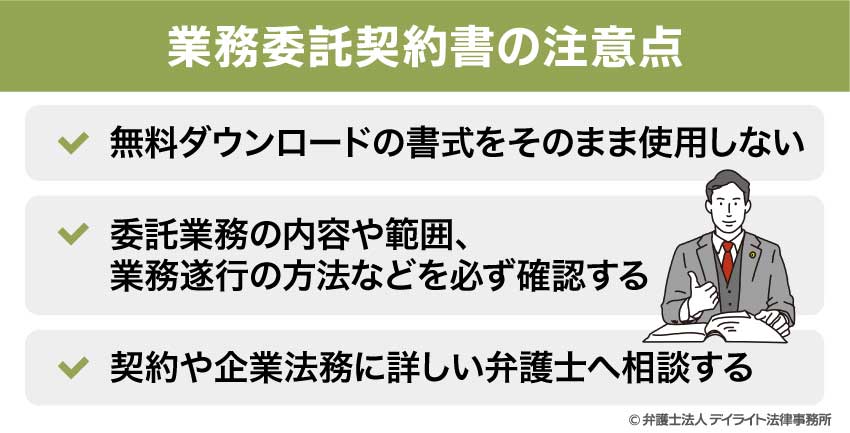
無料ダウンロードの書式をそのまま使用しない
業務委託契約書のひな形は、このページのリンク先にあるひな形以外にも、インターネット上でさまざまなひな形を無料でダウンロードすることができます。
しかし、契約書のひな形は、あくまでもサンプルとして基本的な内容を記載したものであって、そのまま使用すればよいというものではありません。
特に業務委託契約は、委託する業務の内容によって、注意点や記載方法が異なります。
また、委託する業務の内容は、個々の取引に合わせて具体的に記載する必要があるため、ひな形をそのまま流用することはできません。
したがって、業務委託契約書のひな形を入手した後は、委託する業務の内容や当事者間の合意内容を正しく反映したものになるよう、当事者間で確認しつつ、加工していく必要があります。
委託業務の内容や範囲、業務遂行の方法などを必ず確認する
業務委託契約書において、委託業務の内容や範囲が正しく記載されているか、具体的な記載となっているか、契約書の記載が曖昧で不明確な点はないか、必ず確認しましょう。
また、受託者の立場からは、業務遂行の方法が記載されている場合にはその方法が現実的に可能なものかどうか、過度な負担とならないかどうかをよく検討する必要があります。
受託者の立場では、委託業務の内容・範囲や業務遂行の方法の記載が抽象的であいまいだと、あまりにも過剰な義務や責任を負わされてしまうおそれがあります。
この点の確認を怠ると、受託者は予想外のリスクや損害を被ることとなりかねません。
受託者は、必要に応じて契約交渉の段階で委託者と話し合って、ご自身がどのような業務を委託されるのかを事前にしっかりと理解しておきましょう。
契約や企業法務に詳しい弁護士へ相談する
契約や企業法務に詳しい弁護士に相談することで、適切な業務委託契約書を作成・締結することが可能となります。
契約や企業法務に精通している弁護士であれば、当事者が想定できていなかった法的リスクも含めアドバイスをしてもらい、リスクを把握した上で対応することができます。
業務委託契約を作成・締結する際の助言のほか、相手方が作成した契約書案のチェックや修正も依頼することが可能です。
特に、顧問弁護士を依頼している会社であれば、企業の担当者は顧問弁護士に気軽に契約書のことを相談できます。
以下のリンク先で、顧問弁護士の必要性やメリットについて説明しています。
業務委託契約書のよくあるQ&A
![]()
収入印紙は必要?
委任(準委任)契約に該当する場合
業務委託契約書の内容が委任(準委任)契約に該当する場合は、原則として、印紙税法における課税文書に該当しないため、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、後述するとおり、継続的取引の基本となる契約書に該当する場合には、「第7号文書」として印紙税法における課税文書に該当することとなり、収入印紙を貼る必要があります。
請負契約に該当する場合
業務委託契約書の内容が請負契約に該当する場合は、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙の金額については、以下の表のとおり、契約の金額に応じて定められています。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
継続的取引の基本となる契約書に該当する場合
業務委託契約書の契約期間が3か月を超え、かつ更新の定めがあるときは、継続的取引に該当し、契約書1通ごとに4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
![]()
業務委託契約書を個人間で締結できる?
業務委託契約の当事者は、企業であるか個人であるかは問われません。
例えば、個人であるフリーランスの間で業務委託契約を結ぶこともできます。
企業間だけでなく、個人間の業務委託契約でも、後のトラブルを防ぐために、業務委託契約書を作成すべきでしょう。
まとめ
以上、業務委託契約書の意義や書き方、注意点について解説しました。
業務委託契約書は、日常的に頻繁に用いられている重要な契約です。
委託業務の内容に応じて記載すべき条項や記載の仕方が変わりますので、この記事で紹介しているひな形や書き方、注意点などをふまえて、業務委託契約書の内容を正しく理解することが大切です。
そして、契約書の作成や修正については、できるだけ弁護士に相談しておくことが望ましいです。
デイライトでは、企業法務に注力する企業法務部に所属する弁護士が複数所属しており、様々な業務委託契約書の作成やチェックといったリーガルサービスを提供しております。
顧問弁護士としても多くの企業の皆様にご利用されております。企業の顧問弁護士であれば、困ったときにいつでも随時、相談できます。
お困りのことがあればご相談ください。